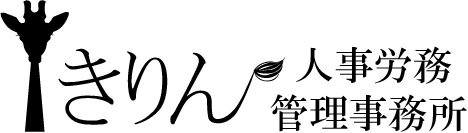介護休業給付・・・要介護状態とは?
育児休業の取得については、政府がかなりの勢いで促進していますが、今後は介護休業についても注目が集まって来るでしょう。
出産育児で離職する方が大分減少時、かつてのM字曲線が消滅したと言われています。
最近では、親の介護または奥様の介護などで、離職を余儀なくされる相談も増えてきています。
ご家族の介護を必要とする従業員が利用できる制度として、育児休業と大変よく似た制度で「介護休業」の制度があります。
国の雇用保険から支給される「育児休業給付金」とならんで「介護休業給付金」の制度もございます。
育児休業は、「子が1歳に達するまで」(延長制度あり)ですが、
介護休業は、「要介護状態の家族を介護する期間」(上限93日間)となっています。
「子が1歳」は分かりやすいですが、「要介護状態」について詳しくご説明いたします。
※介護休業給付金の受給には、他にも要件があります。
※また、企業への支援として「両立支援助成金」の活用もご検討ください。
「要介護状態」とはどのような状況なのかをご説明いたします。
常時介護を必要とする状態に関する判断基準
介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、
常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。
ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、
介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、
事業主は柔軟に運用することが望まれます。
「常時介護を必要とする状態」とは、以下の【1】または【2】のいずれかに該当する場合であること。
- 【1】介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
- 【2】状態(1)~(12)のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。
| 項目\状態 | 1(注1) | 2(注2) | 3 |
|---|---|---|---|
| (1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) | 自分で可 | 支えてもらえればできる (注3) | できない |
| (2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない |
| (3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (4)水分・食事摂取(注4) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (5)排泄 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (6)衣類の着脱 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (7)意思の伝達 | できる | ときどきできない | できない |
| (8)外出すると戻れない | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
| (9)物を壊したり衣類を破くことがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある (注5) |
| (10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
| (11)薬の内服 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
| (12)日常の意思決定(注6) | できる | 本人に関する重要な意思決定はできない(注7) | ほとんどできない |
- (注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
- (注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
- (注3)「(1)座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
- (注4)「(4)水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
- (注5) (9)3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
- (注6)「(12)日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
- (注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。